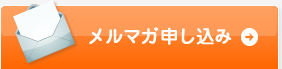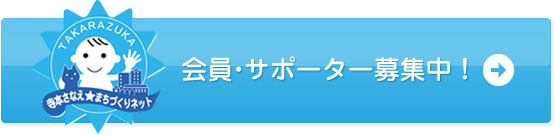消防団年末特別火災警戒活動出発式にて
2023年12月29日
 年内最後の公務は仕事納めの翌日、消防団年末特別火災警戒活動出発式です。午後8時に西谷ふれあい夢プラザ駐車場に消防団本部と10分団が集結。わがまちの火災警戒に向かう団員の皆さまに、市長・議長・議員有志で感謝と激励の思いをお伝えしました。
年内最後の公務は仕事納めの翌日、消防団年末特別火災警戒活動出発式です。午後8時に西谷ふれあい夢プラザ駐車場に消防団本部と10分団が集結。わがまちの火災警戒に向かう団員の皆さまに、市長・議長・議員有志で感謝と激励の思いをお伝えしました。
宝塚の北部、西谷地域へは宝塚駅から車で約30分。山林に囲まれた南北15㎞×東西5㎞の農村地帯です。面積こそ市域102㎢の3分の2を占めながら、人口は令和3年12月で2267人(市全体の1%)とピーク時の半分まで減少。高齢化率が46.6%。消防団もひとつの分団が十数人になってしまって、数年前に年齢の上限が廃止されました。
きびしい状況ですが、初期消火も災害時の対応も消防団にかかっています。
ふだんは都市部へ勤めに出かけ、戻れば村の役がある。まち育ちにはここでの“当たり前”が衝撃でした。新人議員たちにも実感してほしいのですが、私も息子が小学生の頃は(ワンオペ家庭で)夜の西谷行きは難関だった。
子育て真っ最中の議員の分までお見送りしようと思った月夜の晩です。
市議会70周年記念シンポ「ガラスの天井」企画を提案
2023年12月12日
 世界経済フォーラムが公表した「ジェンダーギャップ指数2023」で、わが国は0.647、世界146か国中125位と相変わらずの低迷ぶりを見せた。その原因が政治分野での女性比率の低さにあることは周知のとおりで、国も政党も是正に向けて動き始めている。
世界経済フォーラムが公表した「ジェンダーギャップ指数2023」で、わが国は0.647、世界146か国中125位と相変わらずの低迷ぶりを見せた。その原因が政治分野での女性比率の低さにあることは周知のとおりで、国も政党も是正に向けて動き始めている。
一方で、昨年の統一地方選において地方議会における女性比率が伸びを見せる中、わが宝塚市議会が「女性過半数」(54%)を実現、全国第2位と報道され注目された。※現在52%
市長が女性、議会は男女半々という自治体はかなりレアで、市民から「生活者目線」「子育て支援や女性施策が充実する」など期待される一方、「女性議員が増えても市政は変わらない」「有能なら性別はどうでもよし」という声も少なくない。一説では、「女性議員が3人いるか否かが変わり目」と言われているが、どうなのか。
男女共同参画社会の実現に向け、また多様な住民を代表する自治体議会であるために、ようやくスタート地点に立てた議会として、これからめざすべき方向と課題について、国会議員、組織・企業のリーダー、メディア関係者、学識を招いて考察する。
宝塚市議会70周年記念事業で行うシンポジウムについて、会派代表者会でわが市民ネット宝塚から提案した内容です。
仮タイトルは「『ガラスの天井』を打ち破れ」。基調講演の講師に野田聖子氏(前内閣府特命大臣・男女共同参画ほか)、パネルディスカッションのパネリストには学識、メディア、女性議員比率の高い議会、地元で活躍する女性の名前を挙げました。
※画像は統一地方選後の議会報かけはし第260号表紙
一般質問☆通告しました
2023年12月07日
今回は以下4項目にわたって一般質問を行います。
【質問事項1】犯罪被害者等に寄り添った支援に向けて
1.本市における犯罪被害者等支援の現状について
2.日常生活の支援、居住の安定、精神的な被害回復等のための庁内連携は十分か
3.県との連携について
4.啓発に向けた取り組みについて
ア.公共施設や商業施設等に啓発用自動販売機の設置を
【質問事項2】「湯のまち宝塚」の継承に向けて
1.宝塚温泉の歴史と魅力を伝える拠点の整備を
【質問事項3】職員の採用について
1.就職氷河期世代の職員採用の現状と今後について
2.「令和5年度司法試験を受験した者」を採用する意図は何か
【質問事項4】ハラスメントのない宝塚市をめざして
1.パワハラ、セクハラ、マタハラ等各種ハラスメントの実態は
2.相談窓口と対応、防止に向けた取り組みについて
3.長によるハラスメントを起こさないことについて
12月13日~18日の4日間、26人中(正副議長を除く)24人の議員が一般質問を行います。寺本さなえは18日(月)10時30分~11時30分に登壇。ぜひ傍聴にお越しください。ネット中継もご覧いただけます。
http://www.city.takarazuka.hyogo.jp/gikai/
13代目「生」石を積みに
2023年12月03日
 阪神大震災の犠牲者を悼む「生」の石積みオブジェづくり2日目に参加しました。5月の大雨で前の「生」が流れてしまったので、積み直し。この繰り返しが「再生」の象徴となって、13代目です。
阪神大震災の犠牲者を悼む「生」の石積みオブジェづくり2日目に参加しました。5月の大雨で前の「生」が流れてしまったので、積み直し。この繰り返しが「再生」の象徴となって、13代目です。
今年も作者で現代美術家の大野良平さんの指揮の下、市民有志150人が武庫川・中洲での作業に汗を流しました。ロケーション良好、物語あり、(めったにしない)力仕事をみんなでやるのが楽しく、達成感は◎!
学生さんと親子連れが増えたなぁ。というのが今日の感想です。
軍手長靴スタイルから急いで着替えて、午後から京都へ向かいます。
#議員あるある ☆マルシェと韓紙工芸展示会
2023年11月26日
TIFA広報委員会が午前中に変更になってしまったので、ひそかに楽しみにしていたジャワの人形劇(宝塚ぼうさい劇場2023)を諦め、午後は市立文化芸術センターへ。
㈱ラジュネス企画の田中準子さんが主催する「宝塚華マルシェ」は、宝塚歌劇団OGのショーを中心にアクセサリーやおしゃれ雑貨等の販売ブースと美容コーナーを展開されています。このたび歌劇休演で深刻なダメージを受けている商業者を応援しようと始められたのが「エール宝塚」。イベントやSNSを通じてお店の魅力を紹介されています。
サブギャラリーでは、韓紙工芸家具展示会が始まるところでした。公民館でおなじみの黄恵子さんとお弟子さんの作品がずらり。韓紙を幾重にも貼り合わせて作る調度品の繊細さと美しさは感動もので、独特の色合いに魅了されます。
にぎわうセンターを後にして、報告ごで3カ件、介助犬シンポジウムへは間に合わず、「てんてん会議」(宝塚現代美術てんてん)に顔を出し・・・。
コロナが5類になって以降、イベントや勉強会が復活して、週末はほぼ出ずっぱりです。重なり合う催しを、少しでものぞきたい気持ちと中座する心苦しさとの葛藤は、まさしく“議員あるある”。
そして、この日の締めのシャンソンライブへ急ぐ夜道でハプニングが起きました。続きはまた。
12月議会始まる
2023年11月20日
第5回宝塚市議会が始まりました。会期は12月25日までの36日間。
最初に、閉会中に審査を行った令和3年度一般会計・特別会計決算を全会一致で認定しました。
市長提出議案は、補正予算16件、条例の制定・改正10件、市道路線の認定2件、人事案件3件、阪神水道企業団関係1件と少なめですが、副市長2人体制への議論に注目しています。
市民からの請願は1件。請願第4号「健康保険証の存続を求める請願」について、代表紹介議員の寺本が趣旨説明を行いました。請願者は兵庫県保険医協会北阪神支部北阪神支部と宝塚医療生活協同組合。マイナ保険証の一本化に対する懸念に言及されています。
本会議の後は広報広聴委員会を開催しました。夜は人工芝問題のオンライン意見交換会です。
SSW
2023年11月12日
新大阪で開催された2023年度日本学校ソーシャルワーク学会近畿ブロック研修会に出かけてきました。
基調講演「子どもの育ちと学びを考える
子どもの権利・こども基本法を手がかりに」
末富 芳 先生(日本大学)
シンポジウム「子どもの学校生活を豊かにする仕組みづくり」
武田緑さん、北村将さん、大台賢史さん
議会報告会
2023年11月11日
 男女共同参画センター
男女共同参画センター
第129回近畿市民派議員交流学習会
2023年11月10日
第一部 公共施設の統廃合にどう向き合うか
①報告:豊中市の『公共施設総合管理計画』について
②基調講演:森 裕之さん
第二部 行政内部の連携、行政と民間との協働について
①基調講演:中川幾郎さん
②複合施設「ショコラ」の行政内連携、民間との協働について
豊中市職員(ショコラ館長、こども、生活支援の各担当者、
隣接する小中一貫校の校長または教頭)
③ショコラおよび周辺で活動する民間団体からの報告
香害をなくす議員の会
2023年11月05日
 オンライン
オンライン
シングルマザー
2023年10月22日
 尼崎市立女性センター
尼崎市立女性センター
松江市姉妹都市交流55周年記念
2023年10月22日
 ソリオホール
ソリオホール
香害オンライン署名にご協力を!
2023年10月07日
 「香害」に苦しむ人が増えています。柔軟剤、合成洗剤、消臭剤、芳香剤などの、主に香りのある日用品で体調不良が生じる被害です。とくに、香りや抗菌・消臭作用を持続させるマイクロカプセルなどが製品に使用されるようになってから、香害被害が拡大しました。
「香害」に苦しむ人が増えています。柔軟剤、合成洗剤、消臭剤、芳香剤などの、主に香りのある日用品で体調不良が生じる被害です。とくに、香りや抗菌・消臭作用を持続させるマイクロカプセルなどが製品に使用されるようになってから、香害被害が拡大しました。
この署名は、メーカーにマイクロカプセルなどの「長続き」製法をやめてもらうよう訴えるものです。
マイクロカプセルにはプラスチックが多く含まれており、洗濯のたびに川から海へ流出して環境汚染を引き起こす問題も深刻です。
ぜひ皆さまの1票を! クリック→賛同していただくだけで大きな力になります。 拡散もお願いします。
https://00m.in/Lml8R
発信者:香害をなくす議員の会★香害をなくす連絡会★カナリア・ネットワーク全国(患者会) #香害は公害
政策サイクルと議会成熟度評価
2023年10月01日
 (公財)日本生産性本部が開催する第1回「政策サイクル推進地方議会フォーラム」報告会にオンラインで参加しました。テーマは「住民価値を創造する地方議会へ ~議会からの政策サイクルと成熟度評価の意義」。
(公財)日本生産性本部が開催する第1回「政策サイクル推進地方議会フォーラム」報告会にオンラインで参加しました。テーマは「住民価値を創造する地方議会へ ~議会からの政策サイクルと成熟度評価の意義」。
「地方議会習熟度評価モデル」は、議会改革を議会活動の最終的な到達点である住民福祉の向上につなげていくこと、 議会改革のバージョンアップをはかること、 従来の議会評価に見られた課題を克服することを目的として2020年に開発されました。住民を起点とする政策立案・提言や議案審査、執行機関の監視活動、議会からの政策サイクルの作動による議会の価値創造プロセスに焦点をあて、 機関としての議会を包括的に評価することをめざしています。※「議会プロフィール」「成熟度評価」の2つのツールで構成。
北川正恭・早稲田大学名誉教授は、基調講演「善政競争できる地方議会をめざす」で、地方議会が長らく単なる監視機能と貶められてきたこと、「民意の反映機関」として議員間討議を踏まえて積極的に政策提案していく必要性を強調、評価モデルの導入で首長と議会の善政競争の輪が広がってほしいと括られました。
江藤俊昭・大正大学社会共生学部教授は、「政策に強い議会とは――議会からの政策サイクルの意義とそのバージョンアップ」をテーマに課題提起。「住民自治の根幹」としての議会を作動させる意義と、地域経営の本丸である総合計画や財政にも関わり、4年間の通任期での活動を展開する必要性を訴えられました。(続く)
一般質問☆通告しました
2023年09月20日
今回は以下2項目について一般質問を行います。
【質問事項1】宝塚南口駅周辺のこれからのまちづくりについて
1 旧宝塚ホテルの移転、ツインタワーマンション完成に伴う周辺環境への影響について
2 再開発でできたサンビオラの現状と課題について
3 中心市街地である宝塚南口駅周辺の活性化における市の役割と責任について
ア 住民や来訪者の居場所(カフェ併設の図書館など)と各種サービスのそろう場づくりに向けて
イ 地域住民や商業者、専門家との協議は
ウ 「宝塚大会議」に期待されること
エ 阪急阪神ホールディングスとの包括連結協定がめざすもの
【質問事項2】人工芝をめぐる環境問題と人体への影響について
1 市立花屋敷グラウンドほか公共施設における人工芝の敷設状況について
2 人工芝施設におけるマイクロプラスチック流出抑制対策について
3 人工芝と充填剤によるPFAS(有機フッ素化合物)汚染について
ア 発がん性や環境ホルモン作用のある物質が含まれていると指摘されているが、人体への影響をどう捉え、対応するか。
9月27~29日、10月2日の4日間、正副議長を除く24人の議員が質問します。寺本さなえは9月29日(金)13時45分から登壇。60分間。ご都合のつく方はぜひ傍聴にお越しください。
インターネットでもご視聴いただけます。後日録画配信あり。
https://smart.discussvision.net/smart/tenant/takarazuka/WebView/rd/council_1.html
ストップ! 気候危機
2023年09月15日
 気候危機・議員の会「9.15」庁舎前アクション。
気候危機・議員の会「9.15」庁舎前アクション。
全国の議員有志と市民がつながって「ストップ! 気候危機」の取り組みを発信していきます。
阪神タイガース悲願の18年ぶり優勝に沸く関西。よかった~♪
さっそくあちこちで優勝セールが始まって、「アレ」は流行語大賞になりそうな勢い。そんなわけで私も今日はシマ柄で過ごします。
9月議会始まる
2023年09月01日
 9月定例会初日。山﨑市長から議案 件が上程され、提案理由の説明が行われました。主なものは、2022年度企業会計(上下水道事業、病院事業)決算認定、水道料金の引き上げ、スポーツセンター・花屋敷グラウンド・公民館・文化創造館やソリオホール等の文化施設・市営住宅などの指定管理者の指定など。重要な議案がいくつもあります。
9月定例会初日。山﨑市長から議案 件が上程され、提案理由の説明が行われました。主なものは、2022年度企業会計(上下水道事業、病院事業)決算認定、水道料金の引き上げ、スポーツセンター・花屋敷グラウンド・公民館・文化創造館やソリオホール等の文化施設・市営住宅などの指定管理者の指定など。重要な議案がいくつもあります。
議員提出議案はなし。請願は「教育条件整備のための請願」1件で、紹介議員を代表して寺本が趣旨説明を行いました。
会期は10月10日までの40日間。
悲しい週明け
2023年08月21日
 19日(土)は引き続き政策研究集会へ。午後から文化芸術センターの「きのこと粘菌の市」を楽しんで、帰りに寄ったカフェで出会った人たちと地元課題について話し込むうちに閉店時間超え。1.5㎞圏内でたくさんの人と交流できた週末でした。
19日(土)は引き続き政策研究集会へ。午後から文化芸術センターの「きのこと粘菌の市」を楽しんで、帰りに寄ったカフェで出会った人たちと地元課題について話し込むうちに閉店時間超え。1.5㎞圏内でたくさんの人と交流できた週末でした。
そんな余韻も冷めやらぬまま立ち上げたPCに届いていたまさかの訃報。保育所仲間のYさんです。高校のPTAで一緒に委員をやって、選挙のたびにあれこれ頼み、ばったり会えば子どもたちの近況を伝え合う良き友で、facebookを通じて互いの日常は知っているつもりでいたのです。
「当選おめでとう! 心配してたけど、大丈夫やったやん」
バス停前で声をかけてくれたのが、夢でなければ先月。私は盆踊りに向かう途中、あなたは観劇帰りだったよね。
お茶する約束は果たせないと知りながら、しんどかったのに、あんな笑顔で手を振ってくれたのかと思うと、切なくて――。
日常は、ある日突然そうでなくなり、別の日常が始まるのでしょう。お通夜で流れていた「エリザベート」の歌が頭の中でリフレインしています。
子ども議会
2023年08月21日
子ども議会
気候市民会議とは~気候危機を市民と考える手法~
2023年08月10日
気候危機・自治体議員の会で、環境社会学者の三上直之さん(北海道大学准教授)の講演を聴きました。
「気候市民会議」は、無作為抽出で選ばれた市民による開かれた会議。脱炭素社会への転換をめざし、CO2を削減する方法を議論するもので、西ヨーロッパで研究実践が積み重ねられてきたそうです。日本でも「気候市民会議さっぽろ2020」以来各地に広がって、武蔵野市など自治体が実施するケースも。
無作為抽出、事前の情報提供、参加者主体で熟議、結果は提言等にとりまとめ、効果的な政策・対策を生み出すために活用する。自治体の政策決定や地域での取り組みにどこまで本質的な影響力を持ちうるかはこれからの取り組み次第と聞いて、うちが過去に行ったワークショップの(市民サイドからは明らかな)失敗事例の数々を思い出してしまいました。専門家集団の確保も課題です。
気候市民会議の意義と設計の基本的な考え方、いかにインパクトを高めるかという話に続いて、「杉並区 気候区民会議」について岸本聡子区長から報告がありました。
今世紀半ばにはCO2排出量をゼロにしなければなりません。わが市の取組状況はどうなっているのか、要確認。「気候民主主義」にも注目しています。